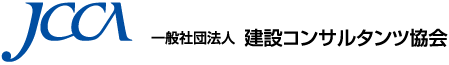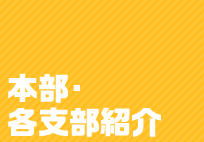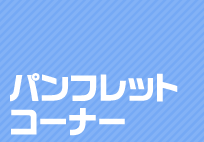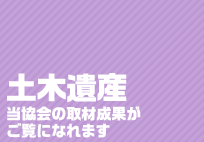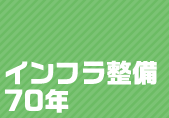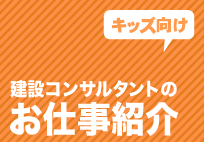昭和46年千葉県水害
災害種別・名称
洪水
昭和46年千葉県水害
体験場所・内容
自宅(木造1戸建て家屋内)
床上浸水被害
体験者の専門分野
河川計画 技術者
被災時の状況
- 高校1年生のときのことである。早朝4時ごろ、水の音で目が覚め、ベッドの上から右手をたらすと、冷たい。『ん??』とっさに昨夜の激しい雨足の記憶がよみがえり、床上浸水していることを理解した。
- ベッドから降りると、水深は床上40cmくらいだ。役場に勤めている父は、昨夜から役場に待機しており、家には母と祖母と私の3人だ。様子を見に行くと、母も祖母も浮力で浮いた畳の上に布団でまだ寝ている。人間の神経はけっこう図太い。たたき起こすと、祖母があわてふためいて騒ぎ出した。
- それまで、千葉県はほとんど水害らしい水害の経験がなかった。総雨量400mmも記録的な雨量ではあったが、防災意識はまったくなかった。雨戸をあけると、庭だったところが濁流で材木や畳がぶつかりながら流れている。危険を感じて、急いで雨戸を閉めた。
被災直後の状況
- 幸い、それ以上水位が上がることはなく、水位が下がり始めたころ、土砂が家の中にたまりはじめたのに気付き、水が引くのにあわせて3人で土砂を掃きだしはじめた。便所の戸もあけて掃除しようとしたら、祖母が『そこはあけるな!』と叫んだ。とっさのところで家中が汚物まみれになるのは免れた。あけていたら家中とんでもないことになっていた。
- たかだか40cm程度の浸水だったが、畳は水で膨れ上がり、とても動かせない。濁流で流れていた畳は、『どうせ使えないし水の流れで動かせるうちに流してしまおう』という不届き者がやってしまったようだ。我が家はそこまで知恵がなかった?ので、膨れた畳はずいぶんあとまで家の中に残り、異臭を放っていた。
教訓
- 水害は水の引き際が掃除のやりどき。あの時期をのがしたら土砂の排出が遅れ、復旧に大きな影響を与えていた。便所も同様。いずれも祖母の知恵である。経験を伝えることは被害軽減や復旧に重要である。災害を契機に、我が家の『便所』も『水洗トイレ』へと生まれ変わった。
- 畳や水にぬれた家財は使えないからと流してはいけない。いたるところに畳や家財が流れ着いており、ずいぶんあとまで誰も片付けることがなかった。被災したからといって、何でもやっていいわけではない。
- 新しいバイパス道路の橋脚に流木がからまっていて流れをせき止め、そこから氾濫したと知ったのは、大学3年生のときに身近な水害を調査するという河川工学のレポートで県の土木事務所から資料を入手したときである。いま考えれば、明らかに橋脚の桁高とスパンに問題があった。住民も日ごろから災害につながるような状況をチェックしておくべきと考える。